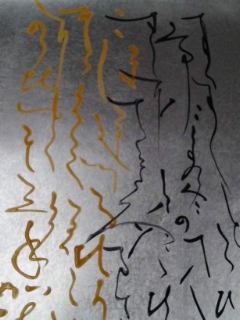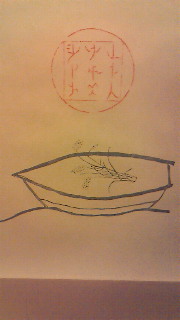古来から石垣はあらゆる文明にあらわれます。
ペルーでのおそろしく巨大で鋭角的な石垣の美しさにその当時の技術を垣間見ました。
日本では古墳時代に墳丘表面にあらわれ、神籠石も七世紀前後の石垣遺構とされます。その後戦国時代の城郭までその技術は忘れ去られます。観音寺城(滋賀県)が城石垣の先駆といわれ、これを手掛けた技術集団が織田信長に雇用された穴太衆で、全国各地に越前衆、尾張衆、長袖衆などがあらわれたのです。
この写真はインスタレーションのようですが、お稽古場のマンションの塀と庭が都市計画道路により長年、懸案されていたセットバックが残念ながらとうとう実現してしまうのです。江戸城と同じ切り込み接ぎの石垣のナンバーリングされました。