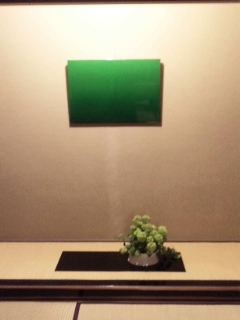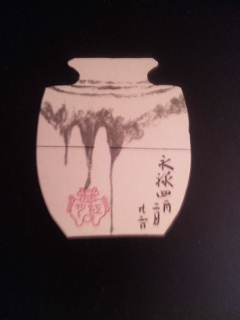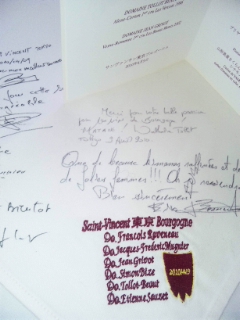歌舞伎座の閉場式にお招きいただきました。
明治22年の開場以来、木挽町に座す歌舞伎座。今の建物は昭和26年に復興開場されました。今日の「都風流」「京鹿子娘道成寺」「口上」「手締式」でその歌舞伎座が幕を閉じます。
本日の拍手の音が神社での祈りの、かしわ手のように清浄で澄み渡り天井から跳ね返るかのように響き、こだましていました。歌舞伎座を惜しみ感謝する観客の心からの思いが音になり満ちていたことに涙が溢れそうになりました。
数々の名場面や歌舞伎座にうかがった様々な思い出が巡りました。
本日、ことのほか美しく覚悟のあった玉三郎の姿。
幕あいで次なる歌舞伎座を設計している隈さんに会い、立ち話。
最後の幕が開くとずらりと羽織袴で勢揃いした役者さん、鳴りものの方々の総勢での古式の手締式は圧巻。この場に立ち会えたことに感謝いたし、まさに御名残歌舞伎座でございました。